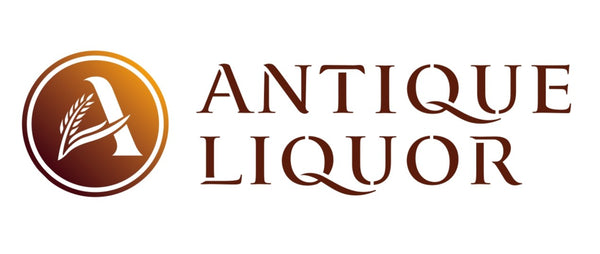オールドボトルウィスキーを探し求める理由について
共有

こんにちは、アンティークリカーの店主です。アンティークリカーでは、同じお値段でもよりパフォーマンスのよい美味しいウィスキーを選び抜いてご紹介しています。そのため、必然的に古き良き時代に流通していたオールドボトル(古酒)を紹介することになりました。
人によっては「オフィシャルの現行品で十分!」と思うことでしょうが、オールドボトルウィスキーの魅力を知ることで、さらに皆様が楽しむウィスキーの世界が一段と広がること間違いないです。ウィスキーの製法やレシピなどは一般に事細かく公開されていないことが多いですが、それでもオールドボトルのウィスキーが一般に現行品を上回るパフォーマンスを見せてくれる共通した理由はあります。正解ではないかもしれませんが、なぜウィスキーのオールドボトルが美味しいのか、私の知識や経験、意見を以下にご紹介できればと思います。

1.大麦の品種の変化(姿を消したゴールデンプロミス)
伝統的なウィスキーの原料は大麦と水、そして大自然だけである...!と、どこかで読んだような気がしますが、それだけウィスキーを作る時に最も重要といえる材料は大麦です。大麦は19世紀以前から改良を重ね、品質が向上し、1960年代になるとウィスキー製造に最も適した品質になりました。 この時期、1968年頃から1980年頃までのウィスキー製造に使用された大麦の品種がゴールデンプロミスと呼ばれる品種でした。この時代に製造されたウィスキーのどれだけがゴールデンプロミスで作られたウィスキーであるかは分かりませんが、この時代をウィスキーの黄金期にした一つの背景ではないかと思います。最近ではゴールデンプロミスを使ったウィスキーは特別なウィスキーとして取り扱われており、転売市場では非常に高いプレミアムが付くほど希少かつ貴重なウィスキーになっています。
しかし、このゴールデンプロミスは残念ながら1980年を境に、急速に姿を消し始めます。 その理由は、ウィスキー製造の「効率」が悪かったためです。より正確にいうと、ウィスキーの大量生産に適していなかったためでした。
大麦でウィスキーを作る際は大麦を糖化させた後、酵母を利用してアルコール発酵を行います。ゴールデンプロミスは、1980年より前までに利用されてきた品種よりもアルコール発酵によるアルコールの生産効率がよく、風味のよい高品質のウィスキーを作るために非常に適していたため、大変人気のある品種でした。
しかし、1980年代に入ってから多くの蒸留所が従来よりもより一層大量生産体制に舵を切る流れになり、ウィスキー作りに利用する麦もゴールデンプロミスから更にアルコール生産効率のよい別の品種に変わっていくようになりました。そのため、1980年代に蒸留されたウィスキーから、だんだんとウィスキーのクオリティが低下していく結果を招いてしまっていました。このような背景もあり、1970年代までに蒸留および樽入れしたウィスキーは平均して品質が良かったのではないかと思います。
年代 |
代表的な麦の品種 |
アルコール生産効率[LPA/トン] |
|
~19世紀 |
Bere |
260 程度と推測 |
|
~1900年代 |
Chevalier |
300 程度 |
|
~1950年代 |
Spratt Archer Plumage Archer |
360~370 |
|
1950年代~1968年 |
Zephyr |
370~380 |
|
1968年頃~1980年代 |
Golden Promise |
385~395 |
|
1980年頃~1985年頃 |
Triumph |
395~405 |
|
1985年頃~1990年頃 |
Camargue |
405~410 |
|
1990年頃~2000年頃 |
Chariot |
410~420 |
|
2000년 以降~ |
Optic |
410~420 |
<表> スコッチウィスキー製造に使用された時代ごとの大麦の品種とアルコール生産量の変遷

2.伝統的なフロアモルティングの相次ぐ中止
オールドボトルウィスキーが現行品より美味しい理由、その二つ目はなんといってもフロアモルティングであることでしょう。スコッチモルトウィスキーを作る際には、まず大麦を糖化させた後、酵母を利用してアルコール発酵を行います。 この時、大麦のデンプン糖化がうまく進むように、大麦を発芽させた「麦芽」にする作業を行うのですが、これをモルティング作業といいます。
このモルティング作業を行う際には、まず数日間水に浸した大麦を取り出し、フロア、つまり床に敷き詰めます。 その後、「モルトマン」と呼ばれる専門家が大麦の水分が全体的に一定に保たれて一定にモルティングが進むようにシャベルで大麦をかき混ぜる作業を行います。大麦から伸びた小さな芽や根が絡み合うことなく、均質な麦芽に変化していくように手助けする作業だそうです。 このモルティング作業だけでも、最低でも数年の修行が必要な作業だそうで、ただシャベルで大麦をかき混ぜるのではなく、職人ならではのスキルがあるようです。このモルトマンの作業によって、大麦の乾燥度合いやモルティング度合いがコントロールされ、後に作られるスピリッツ(ウィスキーの樽熟成前の原酒)の隠れた風味を生み出すとも言われています。
しかし フロアモルティングは大量生産には適しておらず、一定したウィスキーのクオリティ(各蒸留所特有の‘らしさ‘が保たれたクオリティ)を維持することも容易ではなく、何より膨大な労働力が必要なため、近年はドラム式モルティングなどの機械式モルティングが一般化されたそうです。 そのため、オールドボトルウィスキーと現行品ではどうしても香味の違いが発生するそうです。
ちなみに、現在まで一部でもフロアモルティングを維持している代表的な蒸留所としては、スプリングバンク、ラフロイグ、キルホーマン、ハイランドパーク、ボウモア、ベンリアックなどがあるそうです。どれも今でも人気の高い有名な蒸留所ですね。

3.高品質のオーク樽が枯渇
大麦で作ったスピリットを樽に入れて熟成する際、私たちが知っているシェリー樽や、バーボン樽、コニャック樽、ラム樽など、他の種類のお酒を熟成させていたオーク樽を使うことになります。古き良き時代のオールドボトルウィスキーは、このような様々な販売用の美味しいワインや蒸留酒を溜めていた良質なオーク樽を使って熟成していました。シェリーウィスキーやコニャックなど様々な美酒を溜めていたオーク樽は、その美酒を吸い込みます。このようなオーク樽でウィスキーを熟成すると、濃厚な香りの高級ウィスキーが誕生することが多いそうですが、最近は関連法令や市場の需給バランスの影響によってこのような良質な樽を見つけることはほとんど不可能になりました。 これがオールドボトルウィスキーと現行品のクオリティを分ける主な理由になります。
特に近頃最も人気のあるシェリーウィスキーに使われるシェリー樽の場合は、本当にシェリーワインを溜めていたオーク樽ではなく、トーストされたオーク樽の中に安物のシェリーウィスキーを一時的に溜めておくかシェリーワインを塗り付けた程度のシェリー樽の類似品であることが多いのが現実です。このような違いからも、オールドボトルウィスキーと現行品には大きく差が生まれます。昔のシェリーウィスキーのほうが現行品よりも雑味が少なく、フローラルでバランスも良い気がします。
また、オーク樽自体も、昔は十分に育った上質な木を材料として、非常に長い時間をかけて乾燥させて樽を作ったのに対し、最近は最低限の条件を備えた木材で最低限の加工をして樽を作るそうです。そうでないところもありますが、そうせざるを得ない大きな流れがあるようです。 このような違いはウィスキーのバニラ香などの香味に影響を及ぼし、比較的雑味が多くなり、この雑味をピート香や、高水準のアルコール、または長期熟成で消し去る作業が必要となり、結果として繊細で複雑なバランスを維持することが難しくなるとも言われています。 このような理由が、オールドボトルウィスキーと現行品の違いを生み出しているようです。
4.ウィスキー熟成年数表記の意味合いが変化

上の写真は、1970-1980年代初頭に瓶詰め・流通されたシングルモルトウィスキーリンクウッドの12年(OVER)熟成ウィスキーです。このウィスキーはちょうど12年間熟成されたウィスキーでしょうか? この12年という表記は、「原酒の最低熟成年数が12年以上」であることを保証する数字で、それ以上の意味はありません。 つまり、ウィスキーの味を整えるために12年熟成を超えるウィスキー原酒をブレンドして作ることもあるのです。ウィスキー人気が今ほどではなかった1980年代あたりはこれが可能でした。むしろ一般的でした。 1970年代初頭の第1次オイルショック、1970年代後半の第2次オイルショック、そして世界的な不況による一時的なウィスキー生産数や消費量の急激な減少で、やむを得ず生まれた大量の長熟ウィスキー原酒の存在も影響していたことでしょう。
18年熟成、30年熟成のウィスキーを混ぜるなら、18年、30年熟成で発売すればいいのに、なぜ12年なんだ!アホか!」といった意見もあるかもしれませんが、12年熟成表記のウィスキーの目指すところと、18年熟成表記のウィスキーの目指すところが違うからだと思います。 12年熟成表記のウィスキーでも、18年熟成のウィスキーを混ぜて適切なバランスをとったウィスキーと、18年以上のウィスキーだけを混ぜて別の重厚なキャラクターを作り出すこともできるのです。
オールドボトルウィスキーの場合は、このように12年熟成表記であっても実際には12年熟成ではなく「最低12年以上熟成されたウィスキーを混ぜたシングルモルトウィスキー」という意味合いが強かったと思います。 結局、平均的な熟成年数が12年よりも長いのです。 しかし、現代では、麦から燃料から瓶に至るまでのウィスキー生産費用が高騰し、熟成年数の高いウィスキー原酒が不足している状況で、昔のような太っ腹な方法ではウィスキーが作れなくなりました。12年表記のウィスキーは最低12年以上熟成された原酒を使っているけれど「ほぼ12年間熟成されたウィスキー」に近い時代になってきました。
結局、オールドボトルウィスキーは表記年数よりも実際の熟成年数が長いことが多く、現行品より完成度が高いことが多くなるものだと考えています。
5.ウィスキーのオールドボトル熟成の効果

スコッチウィスキーは最低40%以上で作られますが、高いアルコール度数のために瓶詰め後はウィスキーの熟成は進まないと言われます。そのため、いくら瓶詰め時期が古いオールドボトルウィスキーでも瓶詰め後に熟成年数が高くなっていくわけではないです。例えば、1980年に10年熟成ウィスキーとして瓶詰めされたからといって、2023年現在では43年熟成ウィスキーになるわけではないのです。
しかし!
ウィスキー愛好家の諸先輩方の意見を参考に私の経験を踏まえて考えると、樽熟成とは異なるものの瓶詰め後もウィスキーは緩やかに熟成が進むものであろうと思います。オーク樽との相互作業はなくなったものの長い瓶詰め期間中に少しずつウィスキーの香りに影響を与える成分が増えるそうです。そして、妄想に近い予想ですが、瓶詰め後の長期間にわたってウィスキーの分子構造がしっかりと安定し、香りのバランスと調和が良くなるのではないかと思います。いずれの理由であれ、オールドボトルウィスキーは味も香りもバランスもフィニッシュまで現行品より高く評価されることが多いです。
6.ノスタルジックな感性、そしてオールドボトルウィスキーならではの香り

最後に、古酒ならではのノスタルジックな感性もあることでしょう。結局は非論理的な理由なのかと言われるかもしれませんがお酒や食べ物や美術品は感性の領域でもあると考えますし、その雰囲気を含めて楽しむことのできる芸術作品だと思います。 とあるウィスキーが作られた時代を考え、その時代のウィスキーにまつわる歴史話や環境によって、私が今飲んでいるこの一杯のウィスキーにどのように繋がってきたのか、このウィスキーが瓶詰め後、何十年もの間どのような時間を過ごし、私の元までたどり着いたのか、そんなことを考えるのはとても楽しいものだと思います。感性というのは、ウィスキーという文化を楽しむための一つの大事な要素ではないでしょうか。オールドボトルウィスキーを楽しむ多くの方は、このような点も一緒に楽しんでおり、このような魅力にハマってその価値を感じ、大金を支払っている状況だと思えばいいと思います。
そして、その感性の領域から少し実体のある話をするとすれば、オールドボトルウィスキーにある「古酒特有の香り」があると思います。古い本棚や押し入れ、濡れた新聞紙や段ボール箱、など食べ物でもないもので例えられるけれど、深みのある独特な香りとして表現できるものです。このようにオールドボトルウィスキーには現行品にはない古酒特有の香りが、もう一つあり、シェリーやピート、モルトの香りにも重なり合い、融合しながらウィスキーの香りを複雑にしてくれます。ウィスキーは、この複雑さが一体となったバランスを楽しむお酒だと思います。このような点からも、オールドボトルウィスキーは現行品より奥が深くてじっくりと楽しむのに良いのではないかと思います。
7.まとめとあいさつ
この文章は、オールドウィスキーを好きで楽しむ私たちの価値観を理解してもらうために書いた文章でも、私たちの高価な趣味をそうでない人に理解してもらうために書いた文章でもありません。 ただ...。これからますます飲む機会がなくなる貴重で美味しいオールドボトルウィスキーをより広く多くの方々にも飲んで頂きたい気持ちで書いてみました。
オールドボトルウィスキーは一見高価なものばかりと思うかもしれませんが、年数表記ばかりに気を取られることなく美味しいウィスキーを探すのであれば意外とコストパフォーマンスが良いのがオールドボトルウィスキーです。当ショップではそのような貴重でコストパフォーマンスの良いオールドボトルウィスキーをどんどんご紹介できればと思います。