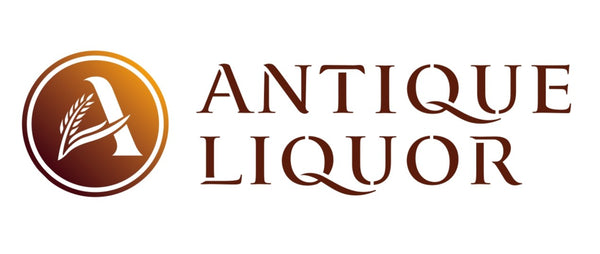世界気候変動は、ウィスキーの質と価格にどのように影響するか
共有

春夏秋冬、四季がはっきりしている日本では、真夏の暑い日も夏だから当たり前で、真冬の寒い日も冬だから当たり前であると考えるのが普通のことかと思います。たまに涼しい夏の日や暖かい冬の日があれど、農家などを除けばラッキーなお出かけ日和くらいでしか考えないのではないでしょうか。
しかし近年の世界気候変動や異常気象は激しさを増し、四季があって気候の変動に鈍感な日本人でも、突発的で激しい天気の変化にびっくりする事が増えてきました。特に夏は気まぐれという言葉では言い表せないほど激しい気候の変化で、ゲリラ豪雨や雹(ひょう)、激しい雷雨や竜巻など、私が知っている日本の天気とは何かが違う気がします。

一方でヨーロッパの猛暑は、作物の生育被害や、降水量の変化だけでなく、土地の質の変化まで影響を及ぼしているようです。ヨーロッパ圏では気温が摂氏40度を超え、最高摂氏46度を記録した猛暑と、干ばつ、そして洪水が同時に発生し、大混乱に陥っているとのニュースを見た記憶もあります。そのたびに私は「ああ、ローカルバーレイの生産量が激減するだろうな」と思ってしまいます。実際に、気候変動などによって年間大麦生産量は40%程度も減ったというヨーロッパのとある地域のサンプルも確認できました。
このように、人類が予想していたよりも早く進行している世界的な気候変動は、すでに産業や生活に破壊的な影響を与えていて、今後の近い未来に世界のウィスキー産業も相当な危機に直面するのではないかと思います。ウィスキーは今よりも贅沢なものとして扱われ、ウィスキーを生産・消費するためには今よりも多くのコストが必要になることでしょう。おそらく以下のようなことが起こるのではないかと思います。 私もただのウィスキー愛好家の一人であって専門家ではありませんが、おおむねの方向性は間違っていないのでは...?と思います。
1) 気候変動による大麦の生産量と品質の著しい低下

最も直接的かつ破壊的な影響を与える要素が、ウィスキー製造に使われる大麦の生産量と品質の低下です。上記に書いたように、近年の急激な気候変動により、生産量が40%以上急減した大麦農場も少なくない状況であり、この流れは今後も続く見通しです。
アサヒビールで有名なアサヒグループの勝木会長は、2023年のインタビューで、「2050年までに地球の温度が摂氏4度上昇するという国連の最悪のシナリオでは、フランスの大麦供給量の18%が減少する」と述べています。パリ協定に明記された目標である2度の温暖化が行われた場合、供給量は10%減少、代表的なビール生産国であるポーランドとチェコの場合、摂氏4度上昇するだけで大麦の供給量がそれぞれ15%、25%減少する可能性があるそうです。
このように大麦の栽培にかかるコストが増加する傍ら、大麦自体の品質は低下し、ウィスキー製造に必要なコストも急激に増加すると思われます。例え、10年後に瓶詰されるウィスキーは2020年前後またはそれ以前に収穫された大麦で作られたウィスキーになりますが、10年後の高い生産コストは10年後のウィスキー価格にそのまま反映されると思います。
2)世界的な食糧難を背景に、穀物の酒類製造に対する非難と社会的コストの増加する可能性あり

そんなことはさすがにありえない!と思うかも知れませんが、ビジネスの分野に問わず、持続可能な経済環境に対する社会的要求と圧力は日を追うごとに強くなってきています。近年の世界人口の継続的な増加や戦争、軍事衝突、気候変動による食料生産量の減少や食料生産能力の減退などの問題により、中長期的に世界的な飢饉を引き起こす可能性があると言われています。 その中で、穀物を飼料として与える家畜の飼育さえも社会的に非難され始めており、やがて大麦やトウモロコシなどの穀物類を食事ではなくお酒に加工することに対する非難も強まるのではないでしょうか。
現在、多くのスコッチウィスキー蒸留所が持続可能な事業への新規投資を増やしています。グレンゴイン蒸留所では、二酸化炭素を捕捉する湿地施設を導入することで、蒸留所の排水を湿地の植物で浄化し、浄化された水を再び管理・利用する循環システムを作ったそうです。この湿地を作ったことで、20種類の植物14,500株と8万匹のミツバチを含む地域の野生生物の避難所にもなり、生物多様性が改善されたそうです。
トマーティン蒸留所も2023年のIcons of Whiskyアワードで今年の持続可能な蒸留所に選ばれた蒸留所で、ウィスキー生産に必要な燃料を伝統的な燃料からバイオマスエネルギーと液化天然ガスに転換し、グレンゴインと同じく湿地を造成して生物多様性改善に貢献しながら、工場処理水を浄化するシステムを導入し、二酸化炭素排出量を削減するために太陽光発電まで行っているそうです。
今後他の蒸留所も今まで以上に持続可能な仕組み開発のために設備投資を強いられるようになりますが、その莫大な費用はどこから賄われるでしょうか?当然販売するウィスキーの値段に上乗せされます。そのために今後のウィスキーの価格は継続的に高くなっていくほかなく、長熟ウィスキーの場合は、もはや目で楽しむしかない価格になるのかもしれません。
3)ウィスキー熟成用樽の製造に使用される上質な天然資源の枯渇

現在、スコットランドのウィスキー事業は一般にヨーロピアンオーク材で作られた樽を活用することが多いそうです。木材の消費には自然破壊の印象を受けますが、森林資源の開発と伐採を並行して行っているため、むしろ世界の環境問題には貢献しているとのことです。しかし問題は環境問題ではなく、ウィスキー熟成用オーク樽に使われる木材資源の生産量と質の低下です。
- オーク樽の排出作用:オーク樽から揮発性芳香物質(アルデヒド)、脂質、タンニン、ラクトンなどの成分を排出する作用。
- オーク樽の吸収作用:樽内部の焦げた部分がカーボンフィルターのように働き、ウィスキーの成分を吸収する作用。
- オーク樽とウィスキーの相互作用:樽とウィスキーの相互作用。相互に構成物質を交換しながら新しい物質が生まれる作用。
- ウィスキーの酸化作用:オーク樽が完全密閉されていないことから生じる蒸発と酸化作用。
ウィスキーの熟成には、上記のように、樽の成分がウィスキーと化学反応を起こしながら風味を育んでいくのですが、気候変動による木材成分の変化、そして木材生育期間の長期化などから、美味しいウィスキーを作るための高品質なオーク樽を確保することが難しくなってきたようです。
また、ウィスキーを熟成させるためのワイン樽やコニャック樽などの特色ある樽の流通が激減しています。ヨーロッパのワイン産業の没落により、高級ワインを溜め込んでいた良質なオーク樽が減少し、ウィスキーを熟成させる樽の選択肢が大幅に減少してきています。
このような理由から、今後高品質、長期熟成のウィスキーは生産コストが倍々に上昇し、18年熟成どころか、熟成年数が表記されたウィスキー全般が手の届かない高級品になってしまう可能性もあるのではないでしょうか。
4) ウィスキー蒸留時に発生する温室効果ガスに対する負担金の増加

ウィスキーづくりといえば、巨大な蒸留器から立ち上る蒸気で代表される蒸留設備のイメージが広く知られていると思います。ウィスキーづくりのための蒸留方式も様々あるようですが、伝統的な上流方式は最新式のガス蒸留器よりも特に多くの熱と二酸化炭素を排出しているそうです。そしてこれが「お金持ちの趣味のために環境を破壊する行為」として避難されているそうです。そのため、近頃の蒸留所は最新の管理設備を導入し、排出される二酸化炭素の量を測定・管理するシステムを導入したり、二酸化炭素を吸収する新しい施設を作ったり、温室効果ガス排出に対する多額の負担金を払わなければならない状況になってきているようです。このような費用はすべて、ウィスキーの価格に反映されることでしょう。
5) 泥炭(でいたん、ピート)確保コストの増加

英国の産業全体が採取した泥炭(でいたん、ピート)のうち、ほとんどの泥炭は一般燃料として利用され、わずか1%だけがウィスキー製造に利用されているそうです。 一般燃料として利用される量が多いこともあって泥炭の埋蔵量は目に見えて減っており、スコットランド政府は2030年までに25万ヘクタールの泥炭地を復元するために2億5千万ポンドを投資すると発表しました。この莫大な投資金は政府の支出ではありますが、結局のところはウィスキー産業にその負担を転嫁するしかないと思います。
上記のような理由で、今後のウィスキー市場は低価格のウィスキーと高価格のウィスキーにさらに二分され、時間をかけて吟味できる高品質のウィスキーはなかなか手に入らない贅沢品になる可能性が高い気がします。そのためにも、好きなウィスキーに関しては、早め早めに手に入れておくといいかもしれません。